生き残りをかけてもがく家電メーカーたち
2020.12.24
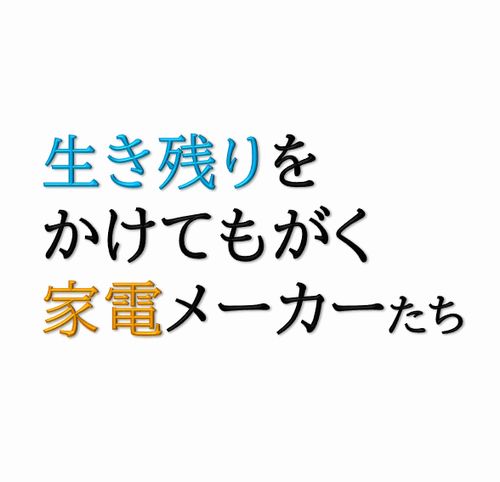
(2020年12月24日メルマガより)
前回のメルマガでは家電量販店のヤマダ電機について書きました。
家電販売ビジネスの縮小に見舞われ、住宅関連事業などに活路を見出そうとしているヤマダ電機のお話です。
ヤマダ電機ほどの規模になると、事業転換も容易ではありません。
ところどころ成長機会はあるものの、いずれもニッチ需要で、ヤマダ電機全体を潤わせるほどのものがありません。
メルマガでは偉そうなことを書きましたが、所詮は外野の意見ですかね。組織全体を賄えるほどの方向性を見つけるのは至難の業ですから、内部の方のご苦労はお察しいたします。
その点、規模の小さな会社は、小さな市場でも生きていけます。雑草のようなもので、隙間や窪地でも充分に生育可能です。
雑草には雑草の生き方がある、ということを理解する者は、強いですよ。
■それはともかく、そもそもヤマダ電機が苦境に陥ったのは、日本の家電産業全体が勢いを失ってしまったからです。
パナソニックも、ソニーも、日立も、東芝も、三菱も、シャープも、かつての勢いはなく、事業再構築を迫られ、方向転換を余儀なくされています。
韓国勢にも中国勢にも勝てず、事業事業の縮小、撤退に追い込まれるその姿には、家電王国といわれた頃の面影は皆無です。
いったい何があったというのでしょうか。
そうかと思えば、規模は大きくなくても、きらりと光る新興家電メーカーも育ってきており、バルミューダのように新規上場し、評価されている企業もあります。
今回は、前回に続き、家電産業について書いてみました。
どうか最後までお読みください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月16日、家電メーカーのバルミューダが、東証マザーズに株式上場しました。
その日の終値は、公募価格の2倍近くになり、時価総額は約298億円に達したといいます。
成熟産業の新興メーカーとしては、上々の滑り出しではないでしょうか。
衰退する国内大手家電メーカー
もっとも日本の家電産業には、かつてのような勢いがありません。とくに、業界を牽引してきた大手企業に元気がありません。
日立も東芝も家電部門を海外企業に売却し、産業材やインフラ部門に経営資源を集中させようとしています。
シャープは、会社そのものが、台湾の鴻海の傘下にあります。
三洋電機はパナソニックの子会社ですが、家電部門を中国企業に売却して10年近くになります。
家電メーカーの雄、パナソニックでさえ、家電からの脱却を目指して、方向性を探っています。
まあ、それも仕方ありません。
人口減少する日本において、これらの企業は、持ちこたえられないほどの大きさになってしまったわけです。
成長期に網を広げるのは正しい戦略です。が、肝心の魚がいなくなったら、大きな網が無駄どころか邪魔になってしまいます。
小さな船で充分な時に、維持費のかかる巨大船は金食い虫でしかありません。網元は、船を処分するか、別の使い道を探すかしないと、経費倒れになってしまいます。
いまの大手家電メーカーが直面しているのはそういう状況ですな。
海外進出にも本気になれない
日本では魚が減っていくかもしれないが、海外では増えているじゃないか。という人がいるかもしれません。
確かにそうです。日本でダメなら海外に行けばいい。
ただ、日本の家電メーカーはことごとく海外進出に失敗しています。
これも、日本国内で充分に潤ってきた時代が長かった悲しさです。海外に売るためには、海外の顧客にあわせたビジネスをしなければなりません。商品も、売り方も、現地にあわせることが重要です。
韓国のように国内市場がもともと小さい国の企業は、海外進出ありきでなければ、それなりの大きさになりません。だから、サムスンやLGなどは、早い段階から、海外進出を含んだ商品づくりや販売のための組織を志向していました。
しかし、日本企業はそうではありませんでした。
日本国内で商売するだけで充分に儲かるので、海外進出を意識するのは、大企業になってからです。商品も販売も、まずは国内仕様となっています。
商品については、国内市場で同程度の技術力を持つライバル企業がひしめいていたため、いきおい似たようなものとなってしまいます。差別化のために機能の付加を繰り返すうちに、使わない機能がいっぱいついた謎の多機能製品が定番となっていきました。
売れるか売れないかわからない海外市場に向けて、今さら、シンプルな商品を作り直すのはリスクですから、日本市場向けの製品をそのまま海外に持ち込む企業が殆どでした。これでは、顧客無視といわれても仕方ありません。
販売においても同じです。海外展開のために、労使関係を含めて組織の在り方を変えるとかややこしい。そんなことをしなくても、国内で充分儲かるやんと、国内担当者からの茶々が入ります。そのうち国内では儲からなくなったものの、今さら、そこに費用や労力をかけられなくなりました。
そこに苦労するぐらいなら、家電部門は海外に売り払って、自社は国内でもっと儲かる分野へ移行する方が、合理的だというものです。
国内家電メーカーの多くが、国内の産業材分野へ軸足を移そうとしているのは、経済行動として、理にかなっていると考えます。
家電から撤退するかつての総合電機メーカー
日本の成長期には、家電から大型電機機械まで扱う総合電機メーカーが、隆盛を誇ったものですが、それも今は昔です。
こうした電機メーカーのなかで、経営戦略の基本通り「選択と集中」を推し進めようというのが日立です。
日立はリーマンショック後の大赤字で目覚めて、猛烈に事業再構築を進めている途上です。
日立が目指すのは、「社会イノベーション事業でのグローバルリーダー」だそうですが、これをかみ砕くと、インフラ分野の御用聞きだということです。
要するに、インフラ分野のことなら、何でもやりますよ。問題解決に取り組むので、何でもお申し付けください。という姿勢ですな。
いわば、物理的な商品(機械)をビジネスにするよりも、それに付随するサービスやソリューションを中心にしていこうということです。
その方向性に向けて、事業の売却と買収を進めています。
東芝はもっと早い時期から「選択と集中」に取り組んできました。
しかし、原子力事業への集中投資が裏目に出てしまいました。福島の事故以来、原子力事業の未来が描きにくくなり、莫大な投資が無駄となってしまいました。
そのうえ、2015年には、社内に根の深い会計上の不正が多く見つかり、ダブルパンチで破綻寸前に追い込まれてしまいました。
そこからの東芝は涙なしには語れません。金になるものは何でも売却し、サザエさんのスポンサーもおりて、破綻を逃れるのに精いっぱいでした。
何とか破綻は回避できたものの、今では、柱となる事業がない状態です。まさに白紙からの出直しですな。
こちらも、「インフラサービスカンパニー」を目指すということです。たぶん日立と似た方向性を志向しているのでしょうが、具体的な中身は見えません。
でも、ゼロからのスタートなので、案外、面白い存在かもしれませんよ。
これに対して、全社的な選択と集中をするのではなく、それぞれの分野で分散的に儲ければいいやん、というのが三菱電機です。
同社はバランス経営と称していますが、要するに、各事業部に権限を与えて、各自が生き残り策を考えなさいというやり方です。
いわば弱者の戦略の集合体で、規模的なパワーは活かせませんが、不確定な時代にとにかく生き残るという意味では、理にかなっています。
業績不振が目立つパナソニック
そんな大手家電メーカーの中でも、パナソニックの不振が目立ちます。
パナソニックといえば、日本の家電メーカーのトップに長く君臨し、強者の名をほしいままにしてきた企業です。
とくに1970年代、80年代の「強者の戦略」は、あまりにも盤石で、絶対王者といってもいい存在でした。
ところがコロナ禍の現在、パナソニックは、1人負けといいたくなるような状況です。
この記事を読むと、パナソニックの株式時価総額は、2.6兆円。これは、2008年当時から比べると、4%マイナスです。
これに対して、ソニーの時価総額は11.4兆円。これは、2008年の6倍です。
ちなみに、パナソニックの売上高、7兆5千億円。純利益、2257億円。
ソニーの売上高、8兆2千億円。純利益、5821億円です。(両社とも2020年3月期)
パナソニック(当時は松下電器)が絶対王者だった時代は、ソニーといえばいつ駆逐されるかもしれない弱者企業だったはずです。
なにしろ創業者の松下幸之助氏から「ソニーはうちの開発部隊だ」と揶揄われていたぐらいです。
そんな両社がいまになって立場逆転してしまうとは。。栄枯盛衰を感じずにはいられません。
強者の戦略が使えなくなった
パナソニックの場合、1970年、80年代に盤石なビジネスモデルを築き上げていたゆえに、市場環境の変化への対応に苦労しました。
第一段階は、家電量販店の台頭により、独自の販売チャネルであるナショナルショップの威力がそがれてしまったことです。
パナソニックの強者の戦略は、販売チャネルを押さえることで成り立っていました。いくらソニーが画期的な商品を作ろうとも、後追いでパナソニックが似たようなものを作れば、いちばん売れてしまうのです。販売チャネルを確保する者は、かくも強いのです。
ところが、家電量販店が全盛となると、売り場で比較されるようになり、より商品の力が重要となります。
もっとも、市場シェアトップのパナソニックには、より多くの売り場面積が与えられたので、ここでも同社有利には変わりませんでした。
第二段階は、国内家電市場が縮小し、家電量販店そのものが勢いを失ってしまったことです。
これは深刻です。需要が低迷してしまうと、メーカーは無力です。
家電エコポイントとか、地デジ移行とか、需要を喚起するイベントが終わる2010年頃をピークに、家電の売上は坂を転げ落ちるように縮小していき、如何ともしがたい状況となっていきました。
ただし、この頃には、人口減少により需要が減っていくことは予測されたことですから、メーカーは各社とも、脱家電を志向していました。
柱となる事業が見いだせない
パナソニックも同じです。産業関連機器、住宅設備、車載部品などに活路を求め、家電事業に頼らない体制を作ろうとしました。
特にテスラと提携した電気自動車向けの車載電池については、主力事業にするという強い決意を表していたものです。
ところが、あてが外れました。
天才と謳われながら性格が悪いことで有名なテスラCEOのイーロン・マスクのわがままに散々振り回された挙句「電池は自社で作ることにした」と宣言される始末です。
時間も労力も費用もかかる開発時の一番しんどいところを担わされながら、利益を出す前に放り出されるとは、継子話にも聞いたことがない悲惨さです。
完全にはしごを外されたパナソニックは、柱となる事業をいまだ見出せず、五里霧中にいるといっていいでしょう。
事業再構築に失敗した津賀社長
2012年から社長となった津賀一宏氏の最大のテーマが、脱家電と主力事業の育成でした。
パナソニックほど巨大で歴史のある企業の主力事業を転換するなど並大抵のことではありません。
なにしろ、社内の重鎮やらOBやら謎の関係者やら、歴史を作ってきたと自負する人々が大勢いますから、抵抗勢力だらけです。戦略を作って、ハイ、転換、というわけにはいきません。
津賀氏が、ジャック・ウェルチほど変人で悪辣なら、OBなど糞でも食っとけと嘲笑うこともできたのでしょうが、そうではなかったらしい。
しかもコロナ禍の巣ごもり消費で、家電の売上がなにげに良くて、むしろ存在感を増しています。
津賀氏は、来年、退任する予定ですが、結局、将来に向けて柱となる事業を見出せぬ、脱家電も進まずでは、いったいこの8年間は何だったのだろうと、言われても仕方ありませんな。
脱家電を成し遂げ、業績好調なソニー
対してソニーは、ゲーム関連事業や音楽事業が巣ごもり消費で業績好調です。
設立当初、技術屋の楽園を目指したソニーは、その理念の通り、可能性のある面白い技術の宝庫であったと聞きます。
しかし、1995年に6代目社長となった出井伸之氏は、ソフトとハードの融合を掲げて、ネットワーク事業やエンターテイメント事業に傾倒、大胆な方向転換に踏み切りました。
その過程で、ソニーに蓄積されていた多くの技術が切り捨てられたといわれています。
もちろん非難轟々で、出井CEOの晩年は「最悪の経営者」のレッテルを貼られていたほどです。
後継者に指名されたのは米国人のハワード・ストリンガー氏です。しがらみがより少ない立場だったストリンガー氏は、米国に拠点を置いたままで、エンターテイメント事業のグローバル化と強化を推し進めました。ストリンガー氏自身は、業績不振により解任されますが、後を受けた平井一夫氏が、現在のビジネスモデルを形にしました。
現在、ソニーの収益は、映画、ゲーム、音楽などのコンテンツを活用したサブスクリプションビジネスから得られています。
つまりプレイステーションのオンライン会員などが負担する定額会費が、収益の基盤となっています。
オンラインゲームはグローバルかつ成長産業なので、ソニーの将来は明るいだろうと、株式市場が評価をする次第です。
もっとも、そこにかつての技術企業ソニーの姿はありません。
あのスティーブ・ジョブズも憧れたといわれるソニーは、場合によっては、アップルのような企業になっていたかもしれません。
※アップルの売上高は28兆円、時価総額200兆円超(2020年9月期)
そう思うと、なんとも小粒な会社となったという意見もあります。が、そんなとらぬ狸の皮算用をしても仕方ありませんな。
生き残るために躊躇していられない
そうかと思えば、バルミューダのように、新規上場を果たす新興家電メーカーもあります。
バルミューダだけではありません。ローテクでも、特殊な使用場面に則した商品や尖ったデザインを武器に、ヒットを飛ばす小さな新興メーカーが表れてきており、何気にニッチな盛り上がりを見せています。
いまは、マスを捉えにくい市場なので、むしろ規模が小さいことが、強みとなります。
つまり、大手家電メーカーの規模では、生きにくい産業になっているということです。どうしても家電市場で生きていこうとするならば、ニッチ市場を一つ一つ深掘りしていくことが求められます。
そんな面倒なことやってられん、と大手企業の殆どが、家電事業から撤退したのは、無理からぬことですな。
いずれにしろ、変革期にある産業では、各社が生き残りをかけて知恵を絞り、行動しています。
面白い、といえば失礼に聞こえるかもしれませんが、今の日本は変革期にある産業ばかりなので、決して他人事ではありません。
こんな大企業が生き残るために右往左往しているのだから、われわれ小さな事業者は、躊躇している場合ではありませんよね。
コロナで売り上げが厳しいとか言っていても始まりません。
どうすれば生き残れるのか、すぐ動けばいいのか、あるいはじっと耐えしのぶのがいいのか、自分で考え、決めていかなければなりません。
やはり、戦略がなければ生き残れない。と思う次第です。
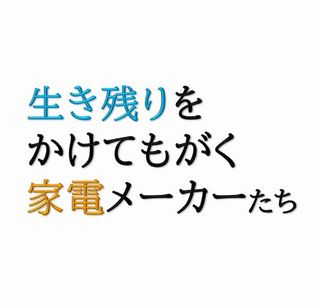
(2020年12月24日メルマガより)
前回のメルマガでは家電量販店のヤマダ電機について書きました。
家電販売ビジネスの縮小に見舞われ、住宅関連事業などに活路を見出そうとしているヤマダ電機のお話です。
ヤマダ電機ほどの規模になると、事業転換も容易ではありません。
ところどころ成長機会はあるものの、いずれもニッチ需要で、ヤマダ電機全体を潤わせるほどのものがありません。
メルマガでは偉そうなことを書きましたが、所詮は外野の意見ですかね。組織全体を賄えるほどの方向性を見つけるのは至難の業ですから、内部の方のご苦労はお察しいたします。
その点、規模の小さな会社は、小さな市場でも生きていけます。雑草のようなもので、隙間や窪地でも充分に生育可能です。
雑草には雑草の生き方がある、ということを理解する者は、強いですよ。
■それはともかく、そもそもヤマダ電機が苦境に陥ったのは、日本の家電産業全体が勢いを失ってしまったからです。
パナソニックも、ソニーも、日立も、東芝も、三菱も、シャープも、かつての勢いはなく、事業再構築を迫られ、方向転換を余儀なくされています。
韓国勢にも中国勢にも勝てず、事業事業の縮小、撤退に追い込まれるその姿には、家電王国といわれた頃の面影は皆無です。
いったい何があったというのでしょうか。
そうかと思えば、規模は大きくなくても、きらりと光る新興家電メーカーも育ってきており、バルミューダのように新規上場し、評価されている企業もあります。
今回は、前回に続き、家電産業について書いてみました。
どうか最後までお読みください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月16日、家電メーカーのバルミューダが、東証マザーズに株式上場しました。
その日の終値は、公募価格の2倍近くになり、時価総額は約298億円に達したといいます。
成熟産業の新興メーカーとしては、上々の滑り出しではないでしょうか。
衰退する国内大手家電メーカー
もっとも日本の家電産業には、かつてのような勢いがありません。とくに、業界を牽引してきた大手企業に元気がありません。
日立も東芝も家電部門を海外企業に売却し、産業材やインフラ部門に経営資源を集中させようとしています。
シャープは、会社そのものが、台湾の鴻海の傘下にあります。
三洋電機はパナソニックの子会社ですが、家電部門を中国企業に売却して10年近くになります。
家電メーカーの雄、パナソニックでさえ、家電からの脱却を目指して、方向性を探っています。
まあ、それも仕方ありません。
人口減少する日本において、これらの企業は、持ちこたえられないほどの大きさになってしまったわけです。
成長期に網を広げるのは正しい戦略です。が、肝心の魚がいなくなったら、大きな網が無駄どころか邪魔になってしまいます。
小さな船で充分な時に、維持費のかかる巨大船は金食い虫でしかありません。網元は、船を処分するか、別の使い道を探すかしないと、経費倒れになってしまいます。
いまの大手家電メーカーが直面しているのはそういう状況ですな。
海外進出にも本気になれない
日本では魚が減っていくかもしれないが、海外では増えているじゃないか。という人がいるかもしれません。
確かにそうです。日本でダメなら海外に行けばいい。
ただ、日本の家電メーカーはことごとく海外進出に失敗しています。
これも、日本国内で充分に潤ってきた時代が長かった悲しさです。海外に売るためには、海外の顧客にあわせたビジネスをしなければなりません。商品も、売り方も、現地にあわせることが重要です。
韓国のように国内市場がもともと小さい国の企業は、海外進出ありきでなければ、それなりの大きさになりません。だから、サムスンやLGなどは、早い段階から、海外進出を含んだ商品づくりや販売のための組織を志向していました。
しかし、日本企業はそうではありませんでした。
日本国内で商売するだけで充分に儲かるので、海外進出を意識するのは、大企業になってからです。商品も販売も、まずは国内仕様となっています。
商品については、国内市場で同程度の技術力を持つライバル企業がひしめいていたため、いきおい似たようなものとなってしまいます。差別化のために機能の付加を繰り返すうちに、使わない機能がいっぱいついた謎の多機能製品が定番となっていきました。
売れるか売れないかわからない海外市場に向けて、今さら、シンプルな商品を作り直すのはリスクですから、日本市場向けの製品をそのまま海外に持ち込む企業が殆どでした。これでは、顧客無視といわれても仕方ありません。
販売においても同じです。海外展開のために、労使関係を含めて組織の在り方を変えるとかややこしい。そんなことをしなくても、国内で充分儲かるやんと、国内担当者からの茶々が入ります。そのうち国内では儲からなくなったものの、今さら、そこに費用や労力をかけられなくなりました。
そこに苦労するぐらいなら、家電部門は海外に売り払って、自社は国内でもっと儲かる分野へ移行する方が、合理的だというものです。
国内家電メーカーの多くが、国内の産業材分野へ軸足を移そうとしているのは、経済行動として、理にかなっていると考えます。
家電から撤退するかつての総合電機メーカー
日本の成長期には、家電から大型電機機械まで扱う総合電機メーカーが、隆盛を誇ったものですが、それも今は昔です。
こうした電機メーカーのなかで、経営戦略の基本通り「選択と集中」を推し進めようというのが日立です。
日立はリーマンショック後の大赤字で目覚めて、猛烈に事業再構築を進めている途上です。
日立が目指すのは、「社会イノベーション事業でのグローバルリーダー」だそうですが、これをかみ砕くと、インフラ分野の御用聞きだということです。
要するに、インフラ分野のことなら、何でもやりますよ。問題解決に取り組むので、何でもお申し付けください。という姿勢ですな。
いわば、物理的な商品(機械)をビジネスにするよりも、それに付随するサービスやソリューションを中心にしていこうということです。
その方向性に向けて、事業の売却と買収を進めています。
東芝はもっと早い時期から「選択と集中」に取り組んできました。
しかし、原子力事業への集中投資が裏目に出てしまいました。福島の事故以来、原子力事業の未来が描きにくくなり、莫大な投資が無駄となってしまいました。
そのうえ、2015年には、社内に根の深い会計上の不正が多く見つかり、ダブルパンチで破綻寸前に追い込まれてしまいました。
そこからの東芝は涙なしには語れません。金になるものは何でも売却し、サザエさんのスポンサーもおりて、破綻を逃れるのに精いっぱいでした。
何とか破綻は回避できたものの、今では、柱となる事業がない状態です。まさに白紙からの出直しですな。
こちらも、「インフラサービスカンパニー」を目指すということです。たぶん日立と似た方向性を志向しているのでしょうが、具体的な中身は見えません。
でも、ゼロからのスタートなので、案外、面白い存在かもしれませんよ。
これに対して、全社的な選択と集中をするのではなく、それぞれの分野で分散的に儲ければいいやん、というのが三菱電機です。
同社はバランス経営と称していますが、要するに、各事業部に権限を与えて、各自が生き残り策を考えなさいというやり方です。
いわば弱者の戦略の集合体で、規模的なパワーは活かせませんが、不確定な時代にとにかく生き残るという意味では、理にかなっています。
業績不振が目立つパナソニック
そんな大手家電メーカーの中でも、パナソニックの不振が目立ちます。
パナソニックといえば、日本の家電メーカーのトップに長く君臨し、強者の名をほしいままにしてきた企業です。
とくに1970年代、80年代の「強者の戦略」は、あまりにも盤石で、絶対王者といってもいい存在でした。
ところがコロナ禍の現在、パナソニックは、1人負けといいたくなるような状況です。
この記事を読むと、パナソニックの株式時価総額は、2.6兆円。これは、2008年当時から比べると、4%マイナスです。
これに対して、ソニーの時価総額は11.4兆円。これは、2008年の6倍です。
ちなみに、パナソニックの売上高、7兆5千億円。純利益、2257億円。
ソニーの売上高、8兆2千億円。純利益、5821億円です。(両社とも2020年3月期)
パナソニック(当時は松下電器)が絶対王者だった時代は、ソニーといえばいつ駆逐されるかもしれない弱者企業だったはずです。
なにしろ創業者の松下幸之助氏から「ソニーはうちの開発部隊だ」と揶揄われていたぐらいです。
そんな両社がいまになって立場逆転してしまうとは。。栄枯盛衰を感じずにはいられません。
強者の戦略が使えなくなった
パナソニックの場合、1970年、80年代に盤石なビジネスモデルを築き上げていたゆえに、市場環境の変化への対応に苦労しました。
第一段階は、家電量販店の台頭により、独自の販売チャネルであるナショナルショップの威力がそがれてしまったことです。
パナソニックの強者の戦略は、販売チャネルを押さえることで成り立っていました。いくらソニーが画期的な商品を作ろうとも、後追いでパナソニックが似たようなものを作れば、いちばん売れてしまうのです。販売チャネルを確保する者は、かくも強いのです。
ところが、家電量販店が全盛となると、売り場で比較されるようになり、より商品の力が重要となります。
もっとも、市場シェアトップのパナソニックには、より多くの売り場面積が与えられたので、ここでも同社有利には変わりませんでした。
第二段階は、国内家電市場が縮小し、家電量販店そのものが勢いを失ってしまったことです。
これは深刻です。需要が低迷してしまうと、メーカーは無力です。
家電エコポイントとか、地デジ移行とか、需要を喚起するイベントが終わる2010年頃をピークに、家電の売上は坂を転げ落ちるように縮小していき、如何ともしがたい状況となっていきました。
ただし、この頃には、人口減少により需要が減っていくことは予測されたことですから、メーカーは各社とも、脱家電を志向していました。
柱となる事業が見いだせない
パナソニックも同じです。産業関連機器、住宅設備、車載部品などに活路を求め、家電事業に頼らない体制を作ろうとしました。
特にテスラと提携した電気自動車向けの車載電池については、主力事業にするという強い決意を表していたものです。
ところが、あてが外れました。
天才と謳われながら性格が悪いことで有名なテスラCEOのイーロン・マスクのわがままに散々振り回された挙句「電池は自社で作ることにした」と宣言される始末です。
時間も労力も費用もかかる開発時の一番しんどいところを担わされながら、利益を出す前に放り出されるとは、継子話にも聞いたことがない悲惨さです。
完全にはしごを外されたパナソニックは、柱となる事業をいまだ見出せず、五里霧中にいるといっていいでしょう。
事業再構築に失敗した津賀社長
2012年から社長となった津賀一宏氏の最大のテーマが、脱家電と主力事業の育成でした。
パナソニックほど巨大で歴史のある企業の主力事業を転換するなど並大抵のことではありません。
なにしろ、社内の重鎮やらOBやら謎の関係者やら、歴史を作ってきたと自負する人々が大勢いますから、抵抗勢力だらけです。戦略を作って、ハイ、転換、というわけにはいきません。
津賀氏が、ジャック・ウェルチほど変人で悪辣なら、OBなど糞でも食っとけと嘲笑うこともできたのでしょうが、そうではなかったらしい。
しかもコロナ禍の巣ごもり消費で、家電の売上がなにげに良くて、むしろ存在感を増しています。
津賀氏は、来年、退任する予定ですが、結局、将来に向けて柱となる事業を見出せぬ、脱家電も進まずでは、いったいこの8年間は何だったのだろうと、言われても仕方ありませんな。
脱家電を成し遂げ、業績好調なソニー
対してソニーは、ゲーム関連事業や音楽事業が巣ごもり消費で業績好調です。
設立当初、技術屋の楽園を目指したソニーは、その理念の通り、可能性のある面白い技術の宝庫であったと聞きます。
しかし、1995年に6代目社長となった出井伸之氏は、ソフトとハードの融合を掲げて、ネットワーク事業やエンターテイメント事業に傾倒、大胆な方向転換に踏み切りました。
その過程で、ソニーに蓄積されていた多くの技術が切り捨てられたといわれています。
もちろん非難轟々で、出井CEOの晩年は「最悪の経営者」のレッテルを貼られていたほどです。
後継者に指名されたのは米国人のハワード・ストリンガー氏です。しがらみがより少ない立場だったストリンガー氏は、米国に拠点を置いたままで、エンターテイメント事業のグローバル化と強化を推し進めました。ストリンガー氏自身は、業績不振により解任されますが、後を受けた平井一夫氏が、現在のビジネスモデルを形にしました。
現在、ソニーの収益は、映画、ゲーム、音楽などのコンテンツを活用したサブスクリプションビジネスから得られています。
つまりプレイステーションのオンライン会員などが負担する定額会費が、収益の基盤となっています。
オンラインゲームはグローバルかつ成長産業なので、ソニーの将来は明るいだろうと、株式市場が評価をする次第です。
もっとも、そこにかつての技術企業ソニーの姿はありません。
あのスティーブ・ジョブズも憧れたといわれるソニーは、場合によっては、アップルのような企業になっていたかもしれません。
※アップルの売上高は28兆円、時価総額200兆円超(2020年9月期)
そう思うと、なんとも小粒な会社となったという意見もあります。が、そんなとらぬ狸の皮算用をしても仕方ありませんな。
生き残るために躊躇していられない
そうかと思えば、バルミューダのように、新規上場を果たす新興家電メーカーもあります。
バルミューダだけではありません。ローテクでも、特殊な使用場面に則した商品や尖ったデザインを武器に、ヒットを飛ばす小さな新興メーカーが表れてきており、何気にニッチな盛り上がりを見せています。
いまは、マスを捉えにくい市場なので、むしろ規模が小さいことが、強みとなります。
つまり、大手家電メーカーの規模では、生きにくい産業になっているということです。どうしても家電市場で生きていこうとするならば、ニッチ市場を一つ一つ深掘りしていくことが求められます。
そんな面倒なことやってられん、と大手企業の殆どが、家電事業から撤退したのは、無理からぬことですな。
いずれにしろ、変革期にある産業では、各社が生き残りをかけて知恵を絞り、行動しています。
面白い、といえば失礼に聞こえるかもしれませんが、今の日本は変革期にある産業ばかりなので、決して他人事ではありません。
こんな大企業が生き残るために右往左往しているのだから、われわれ小さな事業者は、躊躇している場合ではありませんよね。
コロナで売り上げが厳しいとか言っていても始まりません。
どうすれば生き残れるのか、すぐ動けばいいのか、あるいはじっと耐えしのぶのがいいのか、自分で考え、決めていかなければなりません。
やはり、戦略がなければ生き残れない。と思う次第です。
コラム
- 2021.01.07:「鬼滅の刃」大ヒットで復活するソニー「全集中の戦略」
- 2020.12.24:生き残りをかけてもがく家電メーカーたち
- 2020.12.10:ヤマダ電機は、大塚家具の救済よりも、家電産業の復活に取り組め
- 2020.11.26:雑草のようにしたたかなワタミの生き残り戦略
- 2020.11.12:井上尚弥はボクシングの未来を拓くか
- 2020.10.29:出前館vsウーバーイーツ
- 2020.10.15:阪神タイガースはいつまでダメ虎なのか
- 2020.10.01:こんな創業は失敗する
- 2020.09.17:リアル「半沢直樹」 JAL再生は、ドラマよりも奇跡だった
- 2020.09.03:「存在意義」を深く考えない創業は頓挫する
- 2020.08.20:創業の成功確率を上げる5つの要件
- 2020.08.06:米国子会社の破綻は、無印良品の終わりの始まりか?
- 2020.07.23:「論語」は最高の自己啓発書であり、最強の実用書だ
- 2020.07.09:孔子の教えは、なぜ簡単なのに伝えにくいのか?
- 2020.06.25:コロナでも生き残る小さな事業の秘訣
- 2020.06.11:経営者は「貞観政要」を読みなさい
- 2020.05.28:経営者は「君主論」を読みなさい
- 2020.05.14:クロージングがうまくいかない時にこそ、営業の真価が問われる
- 2020.04.30:営業として大成したければ、クロージングでは正攻法を貫け!
- 2020.04.16:営業は基本を学べ。正しい知識を持っていると、経験から正しく学べる。
- 2020.04.02:営業を知らない人ほど怪しげな営業をしてしまうのはなぜか?
- 2020.03.19:プレゼンテーションは、ワンパターンでいい。
- 2020.03.05:「深掘り質問」を制する者は営業を制す
- 2020.02.20:営業は顧客の課題を解決する仕事だ
- 2020.02.06:商談の第一声は営業から発する
- 2020.01.23:「テスト受注」は営業の醍醐味だ!
- 2020.01.09:営業成績が上がらないという人は、顧客訪問してませんね。
- 2019.12.26:とっても簡単な地域営業の始め方
- 2019.12.12:新人営業が自信を持つために最初にすること
- 2019.11.28:創業以来の危機に陥ったアシックスは復活できるのか?
- 2019.11.14:井上尚弥がはじめての苦戦から得たもの
- 2019.10.31:ユニクロ会長が怒る「失われた30年」から抜け出すことはできるのか?
- 2019.10.17:サマンサタバサはなぜ紳士服のコナカに買われたのか?
- 2019.10.03:中小零細企業の大半が不要だと言われてしまう理由
- 2019.09.19:ZOZO身売りに見た前澤氏の限界と可能性
- 2019.09.05:ビアードパパのすごい展開力
- 2019.08.22:マイクロソフトはなぜ比類なき復活を遂げたのか?
- 2019.08.08:空前絶後の幸運に見舞われながらも、それゆえに破滅した男の話。
- 2019.07.25:吉本が、これほどマネジメント能力がないとは驚いた
- 2019.07.11:ネットフリックスは、本気のディズニーに勝てるのか?
- 2019.06.27:ぺんてるとコクヨ またかよ!?と言いたくなるお家騒動がらみの揉め事
- 2019.06.13:驚異の高収益企業キーエンスの理由
- 2019.05.30:井上尚弥が導く異次元のボクシングビジネス
- 2019.05.16:WOWOWをV字回復させたサブスクビジネスの本質
- 2019.05.02:ランチェスター戦略で令和を生き抜く
- 2019.04.18:豊臣秀吉に学ぶ「人を動かす」秘訣
- 2019.04.04:令和のランチェスター戦略
- 2019.03.21:それでも生き残る!小さな会社の生き残り術
- 2019.03.07:少子高齢化と人口減少に直面する日本を破綻させなめに我々がすべきこと
- 2019.02.21:吉野家は過去の栄光を捨て去れるのか
- 2019.02.07:「サブスク」ビジネスの衝撃
- 2019.01.24:島田紳助や大前研一が提唱する成功理論・成功術
- 2019.01.10:平成が終わっても、人生は終わらない
- 2018.12.27:サーモス(THERMOS)V字回復の鍵は「接近戦」にあり
- 2018.12.13:カルロス・ゴーン事件が教える組織の腐り方
- 2018.11.29:RIZAPリバイバルプランは結果にコミットするか
- 2018.11.01:アマゾン・エフェクトに対抗する手段はあるのか
- 2018.10.04:ランチェスター戦略が示す3つのマジックナンバー
- 2018.09.20:ランチェスター戦略の中で、いちばん使えるところを教えます。
- 2018.09.06:ボクシング 井上尚弥にあって、山中慎介になかったもの
- 2018.08.23:川淵三郎はなぜ他のスポーツ団体関係者のようにダークサイドに堕ちないのか?
- 2018.08.09:半周遅れのヤフーによる起死回生の逆転戦略
- 2018.07.26:営業は「準備」が9割!
- 2018.07.12:サッカーW杯日本代表はなぜ躍進したのか?
- 2018.06.28:メルカリが破格の期待を集める5つの理由
- 2018.06.14:楽天が携帯電話事業にいまさら参入する理由
- 2018.05.31:スタジオアリスがさらに成長するための方法
- 2018.05.17:私が出会った優秀なコンサルタント
- 2018.05.03:サーモス(THERMOS)の奇跡はなぜ起きたのか?
- 2018.04.19:ワークマンは第二のユニクロになれるのか?
- 2018.04.05:これから営業職につく若い人に言いたいこと
- 2018.03.22:シリアルアントレプレナー「ブックオフ」「俺の」創業者の成功パターン
- 2018.03.08:サンマルクカフェにわざわざ行く理由があるのか?
- 2018.02.22:小さな事業者が新規開拓で成功する方法
- 2018.02.08:「なんでも酒やカクヤス」にみる局地戦の極意
- 2018.01.25:私が生き残っているのは「弱者の5大戦略」を実践してきたからです。
- 2018.01.11:2018年 君たちはどう生きるか(吉野源三郎や宮崎駿とは関係ありません)
- 2017.12.28:AIの時代に、どのような営業が生き残れるのか?
- 2017.12.14:ナイキもアシックスも「SHOE DOG」だ!
- 2017.11.30:TSUTAYAやDMMはしたたかに生き残っていくだろうが限界もある
- 2017.11.16:「シン・ゴジラ」って途中まで面白いけど、後半グダグダじゃないですか?
- 2017.11.02:織田信長が22年かけてできなかった天下統一を、豊臣秀吉がたった8年でできた理由
- 2017.10.19:電気自動車(EV)の時代に日本企業は生き残れるのか
- 2017.10.05:顧客満足度3年連続1位!ドトールコーヒーが最強か
- 2017.09.21:ヤマダ電機が生き残りを賭けて反攻開始!
- 2017.09.07:ドラッグストアが、コンビニを食い物にしている
- 2017.08.24:国内で敵なしのカルビーの将来が必ずしも明るくない理由
- 2017.08.10:君は内山高志を見たか
- 2017.07.27:金本知憲監督はすべての中間管理職の象徴だ
- 2017.07.13:自然界のランチェスター戦略
- 2017.06.29:回転寿司は群雄割拠の戦国時代に入った
- 2017.06.15:小さな会社のM&Aが日本を救う?
- 2017.06.01:AbemaTVは年間200億円の赤字から脱却できるのか?
- 2017.05.18:大阪・堺の超優良企業シマノは、これからも盤石なのか?
- 2017.05.04:知られざる成長産業 コインランドリー業界はどうなっているのか?
- 2017.04.20:新社会人に贈る「1万時間の法則」
- 2017.04.06:野村克也を超一流のプロ野球人にした3つの力
- 2017.03.23:風林火山を旗印に掲げた武田信玄は、戦略家ではなかったのか?
- 2017.03.09:ラスト・ワンマイルの表と裏をおさえよ
- 2017.02.23:鳥貴族の成長はこのまま∞に続くのか
- 2017.02.09:キングコング西野の絵本「えんとつ町のプペル」はなぜ炎上するほど売れているのか?
- 2017.01.26:アマゾンはどこから来てどこへ行くのか
- 2017.01.12:「孫子」を5つのポイントで整理した
- 2016.12.29:真田幸村はなぜ「日本一の兵」になったのか?
- 2016.12.15:セイコーマート・北の最強コンビニはどのようにできたのか
- 2016.12.01:クリスピー・クリーム・ドーナツの大量閉店は、前向きだったのですね
- 2016.11.17:ジーユーがユニクロを超える時、ファーストリテイリングは世界トップになる
- 2016.11.03:ピコ太郎はなぜ世界を席巻したのか?
- 2016.10.20:地域密着営業って何だろう?
- 2016.10.06:繁盛する居酒屋には、現場営業に必要なヒントが満載だ
- 2016.09.22:天下分け目といわれた関ヶ原の戦いはなぜ半日で決着がついたのか?
- 2016.09.08:「世界の山ちゃん」は世界に届くのか
- 2016.08.25:リオ五輪 男子柔道はなぜ躍進したのか?
- 2016.08.11:ポケモンGOは、何をGOしたのか?
- 2016.07.28:営業は純粋な「技術」であり、誰でも身に着けられるものである
- 2016.07.14:金本を信じよ!
- 2016.06.30:せっかく展示会出展しても成果の出ないやり方をしている企業が多すぎる
- 2016.06.16:小さな会社が生き残る秘訣は「ニッチであること」その他には...
- 2016.06.02:びっくりドンキーは弱者のエネルギーに満ちていた
- 2016.05.19:「同率勝算の規則」に則った唯一の成功法則
- 2016.05.05:レスターに学ぶ「奇跡のチーム」を作る3つの秘訣
- 2016.04.21:世紀のちゃぶ台返し!セブンに何があったのか
- 2016.04.07:新社会人に贈る あなたの人生を豊かにする秘訣
- 2016.03.24:コメダ珈琲店に人気があるのは理由がある
- 2016.03.10:小さくても生き残る「局所的な強者」の作り方
- 2016.02.25:「営業の仕組み」を身に着ければ、目標達成に苦しまなくなる
- 2016.02.11:子供に自慢できる人生を送りたいなら
- 2016.01.28:マクドナルドもスターバックスも日本市場をなめるな!
- 2016.01.14:「孫子の兵法」を企業経営に活かす方法
- 2015.12.31:結果を出す人は、手段を目的化している
- 2015.12.17:廃業寸前の負け犬集団が、常勝軍団に生まれ変わったわけ
- 2015.12.03:なぜ「世界トップ企業」を目指すのか?
- 2015.11.19:初めての著作は、なぜ「小説」になったのか?
- 2015.11.05:戦略は実行させなければ意味がない
- 2015.10.22:世界トップ企業への道は「差別化」が開く
- 2015.10.08:世界トップ企業になるために最初にしなければならないこと
- 2015.09.24:サーモス(THERMOS)はなぜ「廃業寸前」から世界トップ企業になったのか?
- 2015.09.10:営業には3つの役割がある
- 2015.08.27:楽天球団は、新しい野球を見せてくれ!
- 2015.08.13:ユニクロは、無印良品と提携せよ
- 2015.07.23:ノキアと日本電産 東西M&A巧者のやり方
- 2015.07.09:ワクワクする仕事しかやりません。
- 2015.06.25:ライザップはなぜ叩かれるのか?
- 2015.06.11:「けっこういい」よりも「並外れてダメ」がいい
- 2015.05.28:戦略には「感動」が必要だ
- 2015.05.14:「孔子」を学ぶ意味
- 2015.04.30:スカイマークはなぜ優遇されながら破綻したのか?
- 2015.04.16:セブンvsミスド 初戦の判定は
- 2015.04.02:任天堂はもう一度天下をとれるのか
- 2015.03.19:ファミマはセブンに勝てるのか?
- 2015.03.05:大塚家具の父と娘はどちらが正しいのか?
- 2015.02.19:成長しないビジネスのロールモデル
- 2015.02.05:100回勝負に持ち込めば絶対に勝てる
- 2015.01.22:キリンビバレッジは逆転できるのか?
- 2015.01.08:「孫子」を活用するための最大のキーワード
- 2014.12.31:「孫子の兵法」を学ぶ
- 2014.12.25:ハウステンボスはどのようにして再建されたのか?
- 2014.12.11:テラモーターズは、なぜオートバイ市場のトップ企業となったのか?
- 2014.11.27:人を動かすシンプルなメソッド
- 2014.11.13:嫌いな顧客を嫌いだと思わなくなる方法
- 2014.10.30:縄文時代が何年続いたか知ってます?
- 2014.10.02:阪神タイガースはなぜ優勝できないのか?
- 2014.09.18:創業塾でのQ&A
- 2014.08.21:コンビニのアイスクリームはどうなっているのか
- 2014.08.07:創業して10年続く人が持っている3つの資質
- 2014.07.24:私が「孫子」を使う理由
- 2014.07.10:「三国志」の戦いで勝敗が決する要因とは?
- 2014.06.26:「孫子の兵法」でみる2014年ワールドカップ日本代表の戦い
- 2014.06.12:マラドーナはなぜ三流監督で終わったのか?
- 2014.05.29:相性のいい顧客を探す方法
- 2014.05.15:営業が不得意な人は、営業なんてしない方が成果が上がる
- 2014.05.01:GoProは、強者になれるのか
- 2014.04.17:マクドナルドは、マイルドヤンキーを狙え!
- 2014.04.03:売れる仕組みが必要な理由
- 2014.03.20:営業プロセスがなければ組織は動かない
- 2014.03.06:ビジネスの設計図を作ろう
- 2014.02.20:彼を知り己を知れば...
- 2014.02.06:ビジョンは営業チームを一丸にする
- 2014.01.23:楽しくなければ営業じゃない!
- 2014.01.09:私がメルマガを書く「立ち位置」
- 2013.12.26:レゴは、なぜ世界第2位の玩具メーカーに復活したのか?
- 2013.12.12:コトラーに教えらえた初心に戻る
- 2013.11.28:日本のモノづくりを復活させるには
- 2013.11.14:レッドブルが世界で52億本も売れた「何か」
- 2013.10.31:ヤフーはどこに行こうとしているのか?
- 2013.10.17:飛び火マーケティングの時代-GoPro
- 2013.10.03:アップルは普通の企業になってしまった
- 2013.09.19:7年後、日本は巨大な展示会場になる
- 2013.09.05:店舗系ビジネスの弱者の戦略
- 2013.08.22:私がイチローから学ぶ3つのこと
- 2013.08.08:脱・人脈の営業
- 2013.07.25:ソーシャル時代の「真実の瞬間」
- 2013.07.11:統計は最強の営業マネジメントツールである
- 2013.06.27:新興宗教のビジネスモデル
- 2013.06.13:進化する教育システムに乗り遅れるな
- 2013.05.30:お医者さんや弁護士さんの営業戦略
- 2013.05.16:できる営業は、負け方が違う
- 2013.05.02:宮崎駿とスタジオジブリについて
- 2013.04.18:差別化は、マイナスせよ
- 2013.04.04:JAL再生にみる企業変革の王道
- 2013.03.21:第3回WBC終戦記念 がんばれプロ野球
- 2013.03.07:マイケル・ポーターの戦略はもう通用しないのか?
- 2013.02.21:王将の餃子は大阪を跳び出すか?
- 2013.02.07:営業チームマネジメントの第一歩
- 2013.01.24:失速したマクドナルドの次の一手は?
- 2013.01.10:阪神タイガースは暗黒時代に戻っていくのか
- 2012.12.27:衰退市場でトップを張る宝島社の戦略
- 2012.12.13:目標は、顧客総取り!
- 2012.11.29:答えのない問題に取り組めるのか
- 2012.11.15:手っ取り早く実績を上げるには
- 2012.11.01:プロ野球は、名選手しか監督になれないのか?
- 2012.10.18:世界王者が世界に挑戦!
- 2012.10.04:新・携帯電話版三国志
- 2012.09.20:安売りせずに売る方法
- 2012.09.06:脳内のリミットを外せ
- 2012.08.23:儲ける方法をタネ明かしする
- 2012.08.09:もうかるビジネスにはタネがある
- 2012.07.26:ステーキを売るな、○○を売れ!
- 2012.07.12:一流の営業になるために絶対に避けられない道
- 2012.06.28:顧客を創造するということ
- 2012.06.14:ビジネスが成立するための3つの要素
- 2012.05.31:理屈で捉えきれない会社もある
- 2012.05.17:戦術は現状を効率的にする。戦略は現状を破壊する
- 2012.05.03:物語風ビジネス書を読んでみよう
- 2012.04.19:市場価値より企業内価値を高めよう
- 2012.04.05:3つの起業家タイプが注意すること
- 2012.03.22:ソニーはどこへ行った?
- 2012.03.08:利益を上げるための最もシンプルな方法
- 2012.02.23:ランチェスター戦略を営業に活かすたった3つのプロセス
- 2012.02.09:日本の電機メーカーはどうすれば生き残れるのか
- 2012.01.26:心理学はビジネスに生かせるのか
- 2012.01.12:水戸黄門の終焉と大阪都構想
- 2011.12.29:「坂の上の雲」を越えていこう
- 2011.12.15:強い現場を作る方法
- 2011.12.01:なぜ落合博満はブレないのか?
- 2011.11.17:小さなお菓子屋さんが描く大きなストーリー
- 2011.11.03:理屈でメシは食えん!でいいの?
- 2011.10.20:iPhone vs iPhone
- 2011.10.06:本質からはじめよ!
- 2011.09.22:アマゾンにチャレンジ!
- 2011.09.08:さらば、スティーブ・ジョブズ
- 2011.08.25:マフィアにビジネスの極意を聞く
- 2011.08.11:たまにはビジネス小説でも読みましょうか
- 2011.07.28:なぜ我々にはマーケティングが必要なのか?
- 2011.07.14:「いい商品」って何ですか?
- 2011.06.30:カリスマ営業を有難がっても意味ないでしょう
- 2011.06.16:ネスプレッソが売れている理由
- 2011.06.02:孫子、ポーター、ランチェスター
- 2011.05.19:足腰の弱い欧米企業、頭の弱い日本企業
- 2011.05.05:斎藤佑樹はプロ野球で通用するか?
- 2011.04.21:ランチェスター戦略って役に立つの?
- 2011.04.07:温泉旅館を蘇らせるには
- 2011.03.24:弱い人をより弱くするのが戦略なのか
- 2011.03.10:タスク管理と時間管理のツール紹介
- 2011.02.24:プレーヤーからマネージャーへ
- 2011.02.10:110兆円の市場に遅れた日本
- 2011.01.27:物語と希望の深い関係
- 2011.01.13:グーグルVSアップル
- 2010.12.30:面白い戦略ストーリーの作り方
- 2010.12.16:残念な人には戦略がない
- 2010.12.02:理屈のない実行はギャンブルですよ
- 2010.11.18:メイド・カフェの営業プロセス
- 2010.11.04:プロ野球球団運営を成功させるには
- 2010.10.21:勝ちパターンの作り方
- 2010.10.07:たまには「哲学」の話をしよう
- 2010.09.23:世紀末都市・アキバ
- 2010.09.09:コンビニ・オーナーというビジネス
- 2010.08.26:もし現場のオッチャンがポーターを学んだら
- 2010.08.12:坂の上に雲は見えない?
- 2010.07.29:システム思考って何だろう
- 2010.07.15:営業は「点取り屋」ではない!
- 2010.07.01:戦略はストーリーで語れ2
- 2010.06.17:戦略はストーリーで語れ
- 2010.06.03:アップルは本当に最強なのか?
- 2010.05.20:営業生産性を上げる構造とは
- 2010.05.06:女子高生と一緒にドラッカーを学ぼう
- 2010.04.22:勝海舟が坂本龍馬に伝えたもの
- 2010.04.08:人をやる気にさせるにはどうすればいいのか
- 2010.03.25:アップルとユニ・チャーム~変革企業の共通点
- 2010.03.11:無料のビジネスって何だ?
- 2010.02.25:営業に必要な戦略的思考
- 2010.02.11:狩猟民族の構想力に学ぼう
- 2010.01.28:農耕営業のススメ
- 2010.01.14:2010年は日本企業のアジア進出元年になる
- 2009.12.31:2009年の携帯とジーンズと餃子
- 2009.12.17:20歳の頃の自分に読ませたい本
- 2009.12.03:日本茶も海外進出している
- 2009.11.19:ダイソンはなぜ売れたのか?
- 2009.11.05:私の考える効率的な営業とは
- 2009.10.22:島田紳助の研究2
- 2009.10.08:フォロワー企業のゲーム
- 2009.09.24:地域密着企業の営業戦術
- 2009.09.10:地域密着企業の経営方法
- 2009.08.27:マクドナルド 一人勝ちの理由
- 2009.08.13:死せる孔明、生ける仲達を走らす
- 2009.07.30:農業は儲かるのか?
- 2009.07.16:キリン、サントリー、アサヒ、オリオン
- 2009.07.02:戦略2、戦術1の法則
- 2009.06.18:いい顧客、悪い顧客
- 2009.06.04:日本で一番大切にしたい会社の戦略
- 2009.05.21:それぞれの「1万時間」を過ごそう
- 2009.05.07:社会起業は一般の起業と何が違うのか?
- 2009.04.23:もし諸葛孔明が経営顧問だったら
- 2009.04.09:物語の力を知ろう
- 2009.03.26:祝!WBC日本代表優勝
- 2009.03.12:小さな池の大きな魚
- 2009.02.26:農業にチャンスあり
- 2009.02.12:機能と情緒--2つの差別化の方法
- 2009.01.29:営業は結果を追ってはいけない
- 2009.01.15:真似したくてもできない事情がある
- 2009.01.01:欲しいものを作ってくれるビジネス
- 2008.12.18:オール・ザット・競争戦略
- 2008.12.04:ゼロ距離を目指す
- 2008.11.20:10/13の市場でビジネスする
- 2008.11.06:ローカルヒーロー花盛り
- 2008.10.23:いい商品を、いい人から、安い値段で買いたい
- 2008.10.09:経営で必要な知恵はすべて三国志で学んだ
- 2008.09.25:HONDAが空を飛ぶ!
- 2008.09.11:緊急性にフォーカスせよ!
- 2008.08.28:楽天グループ迷走す
- 2008.08.14:エコカー開発競争
- 2008.07.31:儲けるための仕組みを作ろう
- 2008.07.17:「黒船」iPhoneの衝撃
- 2008.07.03:野球は言葉でするもんや
- 2008.06.19:大阪の小さなものづくり企業
- 2008.06.05:事業コンセプトにこだわる
- 2008.04.24:黒澤明はなぜ世界進出に失敗したのか?
- 2008.04.10:スタジオアリスに見る市場特化の行方
- 2008.03.13:山形の洋菓子店がフォーカスしたもの
- 2008.02.28:阪神タイガースは獣王無敵か?
- 2008.02.14:薄型テレビ市場2.0 競争の鍵はブランド力か
- 2008.01.31:アシックスの戦略、ナイキの戦略
- 2008.01.17:「日本一の村」改革に挑戦
- 2008.01.03:マネることは差別化の第一歩
- 2007.12.20:駄菓子屋さんの成功要因
- 2007.12.06:P&Gの戦略-強者はこれだけ有利だ
- 2007.11.22:浪速のグローバル企業
- 2007.11.08:良いモノを作りさえすれば売れるのか
- 2007.10.25:巨人軍の凋落は止められるか?
- 2007.10.11:"志"が歴史を変えた--三国志に寄せて
- 2007.09.27:縮小するアパレル市場で生き残るには
- 2007.09.13:ハンバーガー帝国興亡の行方は
- 2007.08.30:日本製航空機は羽ばたくか
- 2007.08.16:織田信長はなぜ徳川家康に正室と嫡男の処分を命じたのか
- 2007.08.02:中小企業にとって仕組みとは
- 2007.07.19:島田紳助の研究
- 2007.07.05:最強のビジネスモデルとは何か
- 2007.06.21:迷った時は最終ユーザーに聞け
- 2007.06.07:弱者には弱者の販売促進がある
- 2007.05.24:一発逆転を狙ってはいけない
- 2007.05.10:豆腐一丁からビジネスを考える
- 2007.04.26:戦略がなければ生き残れない
- 2007.04.12:飲料業界は激変の予感
- 2007.03.29:経営理念こそ究極の差別化
- 2007.03.27:ホッピーはなぜ復活したのか
- 2007.03.15:引越し業の差別化競争時代
- 2007.03.01:コンビニ 本格競争時代に突入
- 2007.02.15:一人勝ちのワナにはまった松下電器
- 2007.02.01:ワインブームのその後
- 2007.01.18:本業がなくなってしまったら
- 2007.01.04:すべてはデジタル化する
- 2006.12.21:携帯電話版三国志
- 2006.12.07:小さな旅行会社の成功法則
- 2006.11.23:織田信長の戦略
- 2006.11.09:小さな市場に焦点を絞る会社は強い
- 2006.10.26:弱者を貫いて強者となった企業
- 2006.10.12:市場シェアの獲り過ぎに注意
- 2006.09.28:小さな市場でヒットを飛ばす
- 2006.09.14:日本酒市場あれこれ
- 2006.08.31:小さな市場で戦え
- 2006.08.17:もう1つの成長産業
- 2006.08.03:ランチェスター戦略が示すこと
- 2006.07.20:チャンスがあることを皆が知っている市場
- 2006.07.06:商品の意味が変わる時
- 2006.06.22:サッカーW杯にみる「戦略とは」
- 2006.05.25:SMPを意識する
- 2006.05.11:"営業嫌い"は会社の責任だ
- 2006.04.27:営業の分かりやすいコトバとは
- 2006.04.13:残りの80%に富を再配分する
- 2006.03.30:とるに足りない80%
- 2006.03.16:狭く、深く掘り進めれば、視界は開ける
- 2006.03.02:日本の消費者は世界レベルに近づいている
- 2006.02.16:ノウハウを捨てよう!
- 2006.02.02:一番、損になることをしよう
- 2006.01.19:技術系小企業が生き残るには
- 2006.01.05:すでに起こった未来
- 2005.12.22:顧客接点がビジネスの命綱
- 2005.12.08:一点集中戦略の落とし穴
- 2005.11.24:松下電器の一点集中戦略
- 2005.10.27:2005年日本シリーズを斬る
- 2005.10.13:例外に注目せよ
- 2005.10.10:成長の壁を乗り越える
- 2005.09.29:常識を少しずらすとチャンスが生まれる
- 2005.09.15:見えない敵と戦うには
- 2005.09.01:最も怖いのは見えない敵だ
- 2005.08.18:不滅の営業手法
- 2005.07.22:いつまで川原で石を売るのですか?(3)
- 2005.07.07:いつまで川原で石を売るのですか?(2)
- 2005.06.23:いつまで川原で石を売るのですか?(1)
- 2005.06.09:年功序列の市場はもう無い
- 2005.05.26:バーガーキング復活
- 2005.03.03:オニツカ錐もみ商法とは(後編)
- 2005.02.17:オニツカ錐もみ商法とは(前編)
- 2005.02.03:売れないのではなく、売っていないんですよ
- 2005.01.20:中小企業が狙う中国市場とは
- 2005.01.05:常識にとらわれない戦略を戦う
- 2004.12.24:小さな企業は逆転の発想で戦え!
- 2004.12.09:ゲーム型競争時代は終わらない
- 2004.11.11:北欧企業にみるランチェスター戦略
- 2004.11.02:UTADA全米進出失敗を斬る
- 2004.08.22:韓国ドラマ、なぜ人気?
- 2002.09.07:戦略とは見えざるもの
- 2002.09.07:営業をシステムとして把握する
- 2002.09.07:組織営業を導入しよう
- 2002.09.07:SMPメソッドとは
- お客様の声:はじめてのマネジメント入門
2019.07.16 2019年7月16日「はじめてのマネジメント入門」セミナー受講後アンケートの声です。※アンケート回収47名のうち、当セミナーの内容がビジネスに ①大いに役立つ15名、②役立つ31名、③あまり役に立たな...
- ランチェスター戦略入門セミナー
- はじめてのランチェスター戦略入門セミナー
- はじめてのマネジメント入門
- ランチェスター戦略入門セミナー



